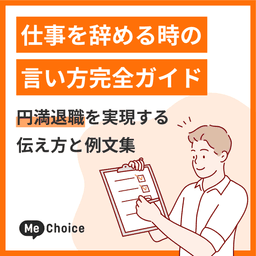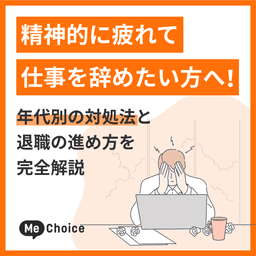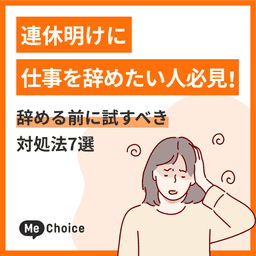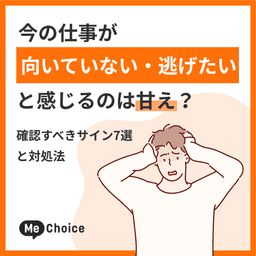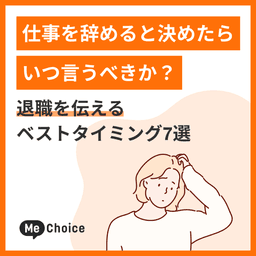

仕事を辞めるベストタイミングは何月?税金・ボーナス・転職活動を考慮した退職時期の選び方
「仕事を辞めるタイミングで損をしたくない…」
「ボーナスをもらってから辞めたいけど、いつがいいんだろう?」
このようなお悩みはありませんか?
退職時期を1日間違えるだけで、社会保険料や税金の負担が増えたり、もらえるはずのボーナスを逃したりする可能性があります。
この記事を読めば、あなたの状況に合わせて最も有利な退職タイミングを見つけることができます。
以下の内容についてご紹介します。
- 目的別で選ぶ最適な退職月
- 退職月を決める際に考慮すべき5つの重要ポイント
- 円満退職を実現するための具体的な手続きの流れ
最適なタイミングで退職し、次のキャリアへスムーズに移行するためにも、まずは転職エージェントに無料相談して、転職市場の動向や求人情報を収集することから始めるのがおすすめです。
今の会社、ちょっと"モヤモヤ"してませんか?
あなたの"会社不満度"をスコア化して、
次のキャリアの可能性をチェック!
仕事を辞めるタイミングとして最適な月5選

仕事を辞めるのに最適なタイミングは、目的によって異なりますが、一般的に求人が増えたり、金銭的なメリットがあったりする特定の月が存在します。具体的には、年度末の3月、夏のボーナス後の6月、上半期の区切りである9月、冬のボーナスと年末調整が完了する12月、そして年始で求人が動き出す1月が挙げられます。
これらの時期は、企業の採用活動が活発化したり、社会保険や税金の手続きがスムーズに進んだりする傾向があります。ご自身のキャリアプランや経済状況に合わせて、これらのタイミングを戦略的に選ぶことが、損の少ない退職とスムーズな転職活動の鍵となります。
【最適な退職月1】3月末退職:年度末で区切りがよく転職先も見つけやすい
3月末は、多くの企業にとって年度の区切りとなるため、退職するタイミングとして非常に適しています。プロジェクトや業務が一段落し、4月からの新体制に向けて人事異動が行われることが多いため、業務の引き継ぎがスムーズに進めやすいのが大きなメリットです。周囲への影響を最小限に抑えやすく、円満退職を目指すうえで有利な時期と言えるでしょう。
また、1月から3月にかけては、4月入社を目指す企業の採用活動が最も活発になる時期です。新年度からの人員補充や新規プロジェクトの始動に伴い、中途採用の求人数が大幅に増加します。そのため、転職先の選択肢が豊富になり、自身のキャリアプランに合った企業を見つけやすいという利点もあります。
【最適な退職月2】6月末退職:夏のボーナスをもらって退職できる
多くの企業では、夏のボーナスが6月下旬から7月にかけて支給されます。ボーナスを受け取ってから退職するというのは、経済的な観点から見て理にかなった選択といえるでしょう。
転職活動中の生活費はもちろん、新しい職場での生活を始めるための準備資金としても活用できます。金銭的な余裕があれば、焦って次の職場を決める必要もなく、じっくりと自分に合った転職先を探すことができます
ボーナスを受け取るためには、一般的に「支給日に在籍していること」が条件となります。そのため、退職日をボーナス支給日以降の6月末などに設定するのが一般的です。
ただし、就業規則によっては査定期間や支給条件が異なる場合があるため、事前に自社の規定を確認しておくことが重要です。また、ボーナス支給直後の退職は心証を損なう可能性もあるため、引き継ぎを誠実に行うなど、円満退職への配慮が求められます。
【最適な退職月3】9月末退職:上半期の区切りで引き継ぎがスムーズ
9月末は、多くの企業で上半期の締めくくりとなる時期です。年度末である3月末に次ぐ大きな節目であり、プロジェクトが完了したり、組織体制の見直しが行われたりすることが多いため、業務の引き継ぎを行いやすいタイミングと言えます。下半期に向けて新しい体制がスタートする直前であるため、後任者への業務の移行がスムーズに進み、会社への影響を最小限に抑えやすい時期です。
また、転職市場においても、10月入社をターゲットとした中途採用が活発になります。下半期からの新規プロジェクトや欠員補充のために求人が増える傾向があるため、転職先の選択肢も豊富です。夏のボーナスを受け取った後、少し期間を置いてから退職を切り出すことができるため、計画的かつ円満に転職活動を進めたい方にはぴったりのタイミングといえるでしょう。
【最適な退職月4】12月末退職:冬のボーナス受給後かつ年末調整が完結する
12月末の退職は、金銭面と手続き面の両方で大きなメリットがあるため、多くの人が選ぶタイミングです。多くの企業では12月に冬のボーナスが支給されるため、これを受け取ってから退職することで、経済的な余裕を持って新年を迎えることができます。
さらに重要なのが、年末調整の手続きです。12月31日時点で会社に在籍していれば、その年の所得税の計算と精算(年末調整)を会社が行ってくれます。退職後に自身で確定申告を行う手間を省くことができるため、税金の手続きに不慣れな方にとっては、このメリットは大きいでしょう。
ボーナスと年末調整という二つの点で利点が重なる12月末は、計画的な退職において絶好のタイミングの一つです。
【最適な退職月5】1月末退職:年始の区切りで新年度採用の求人が豊富
1月末の退職は、冬のボーナスを受け取り、年末年始の休暇で自身のキャリアプランをじっくり考えたうえで行動に移せるタイミングです。年末の繁忙期を避けつつ、年始の落ち着いた時期に退職の意思を伝え、引き継ぎを行うことができます。
転職市場の観点からも、1月は非常に有利な時期です。4月からの新年度に向けて、多くの企業が中途採用の求人を本格的に開始します。特に、冬のボーナス後に退職した人材をターゲットにした求人が増えるため、選択肢が豊富になります。もし次の職場が決まっていなくても1月末に退職し、2月から本格的に転職活動を開始すれば、たくさんの求人の中からじっくりと次の職場を選ぶことが可能です。
退職月を決める際に考慮すべきポイント5選

最適な退職月を選ぶためには、いくつかの重要なポイントを総合的に判断する必要があります。具体的には、ボーナスの支給条件、税金、社会保険料の負担、有給休暇の消化、そして転職先の入社時期という5つの要素です。
これらのポイントを事前に確認し、自身の状況と照らし合わせることで、経済的な損失を避け、スムーズな退職と転職をかなえましょう。どれか一つでも見落とすと、予期せぬ出費が発生したり、転職活動のスケジュールが狂ったりする可能性があるため、計画的に進めることが重要です。
【考慮ポイント1】ボーナス支給日と在籍要件
退職を考える際、ボーナスを確実に受け取ることは経済的に非常に重要です。多くの企業では、ボーナスを受給するための条件として「支給日に在籍していること」を就業規則で定めています。したがって、退職日をボーナス支給日よりも前に設定してしまうと、査定期間中に勤務していたとしてもボーナスを受け取れない可能性が非常に高くなります。
まずは自社の就業規則や賃金規定を確認し、ボーナス支給の具体的な条件(支給日、査定期間、在籍要件など)を正確に把握しましょう。一部の企業では、支給日以降の一定期間の在籍を条件としている場合もあるため、注意が必要です。これらの規定を理解した上で退職日を設定することが、もらえるはずの収入を逃さないための鍵となります。
【考慮ポイント2】税金(住民税・所得税)の支払い方法
退職時期によって、住民税や所得税の支払い方法が変わるため注意が必要です。
住民税は前年の所得に対して課税され、通常は毎月の給与から天引き(特別徴収)されます。6月から12月に退職する場合、退職月以降の住民税は自身で納付する「普通徴収」に切り替わります。
一方、1月から5月に退職する場合は、退職時に5月までの住民税が一括で給与から天引きされることが一般的です。例えば1月退職なら1月~5月分の未納分、3月退職なら3月~5月分の未納分が差し引かれます。
これにより、最後の給与の手取り額が大幅に減る可能性があるため、事前に心の準備をしておきましょう。
所得税については、年の途中で退職し、年内に再就職しない場合は年末調整が行われないため、自身で確定申告を行う必要があります。12月末まで在籍して退職すれば、会社が年末調整を行ってくれるため、この手間を省くことができます。
【考慮ポイント3】社会保険料の負担額
「次の転職先が決まっていない場合」または「転職先は決まっているが、入社日が翌月以降になる(退職した月内に社会保険の空白期間ができる)場合」、社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)は、退職日を1日ずらすだけで負担額が大きく変わる可能性があるため、最も注意すべきポイントの一つです。社会保険料は月単位で計算され、「月末時点に在籍している会社」でその月分の保険料が徴収されます。
例えば、3月31日(月末)に退職した場合、3月分の社会保険料は会社が半額を負担し、給与から天引きされます。しかし、前述の状況で3月30日に退職した場合、3月末時点ではどの会社にも在籍していないことになるため、3月分の国民健康保険料と国民年金保険料を全額自己負担で支払う必要が生じます。
このように、月末日を退職日にするか、その前日にするかで、約1カ月分の社会保険料(数万円程度)の自己負担が発生するかどうかが決まります。転職先が決まっておらず、国民健康保険に加入する場合は、退職日を月末に設定すると、金銭的な負担が最も軽くなります。
【考慮ポイント4】有給休暇の消化期間
退職日を決める際には、残っている有給休暇の日数を考慮することが重要です。有給休暇を完全に消化して退職することで、最終出勤日以降も在籍期間中は給与を受け取ることができます。
まず、自身の有給休暇の残日数を確認しましょう。その上で、業務の引き継ぎに必要な期間を確保しつつ、残りの日数を消化できるような退職日を設定します。例えば、有給が20日残っている場合、引き継ぎに1カ月かかると想定すると、退職の意思を伝えるのは退職希望日の約2カ月前が理想的です。
退職の意思を上司に伝える際に、有給休暇を消化したい旨も合わせて相談することで、スムーズなスケジュール調整が可能になります。計画的に消化することで、収入を確保しながら、転職活動やリフレッシュの時間を十分に作ることができます。
【考慮ポイント5】転職先の入社時期
転職先がすでに決まっている場合、その会社の入社日から逆算して退職日を決めるのが基本です。一般的に、企業が内定を出してから入社を待ってくれる期間は1カ月から2カ月程度が目安であり、長くとも3カ月以内に調整するのが望ましいでしょう。企業は人員計画に基づいて採用活動を行っているため、あまりに長く待たせると入社の意思を疑われたり、内定が取り消されたりするリスクもあります。
内定が出たら、現職の引き継ぎに必要な期間や有給休暇の消化日数を考慮し、実現可能な入社可能日を速やかに転職先に伝えましょう。もし調整が難しい場合は、転職エージェントを利用していれば、担当のキャリアアドバイザーが間に入って交渉してくれます。現職への配慮と転職先への誠意の両方を示しながら、スムーズな移行を目指しましょう。
月末退職と月初退職の違い2選

「次の転職先が決まっていない場合」または「転職先は決まっているが、入社日が翌月以降になる(退職した月内に社会保険の空白期間ができる)場合」、退職日を月のいつにするかは、経済的な負担や手続きの手間に大きく影響します。特に「月末退職」と「月初退職」では、社会保険料の負担、給与計算、失業保険の受給開始時期において明確な違いが生じます。
これらの違いを理解せずに退職日を決めてしまうと、数万円単位の予期せぬ出費が発生する可能性があります。それぞれのメリット・デメリットを把握し、自身の状況にとって最も有利な選択をすることが重要です。
【違い1】社会保険料の負担額が変わる
月末退職と月初(または月中)退職の最も大きな違いは、社会保険料の自己負担額です。社会保険料は、月末時点での在籍状況に基づいて計算されます。
月末日に退職した場合、その月の社会保険料は会社が半額を負担し、給与から天引きされます。これにより、自身で国民健康保険や国民年金に加入する手間と費用を1カ月分抑えることができます。
一方、転職先が決まっていなかったり、再就職までに空白期間が発生したりする状況で月の途中で退職すると、退職した月分の社会保険料が発生しないため、退職した月の国民健康保険料と国民年金保険料を全額自己負担で支払う必要が生じます。この差額は数万円に及ぶため、特別な理由がない限り、月末退職を選ぶ方が経済的なメリットは大きいと言えます。
【違い2】給与計算の締め日との関係
退職日を決める際は、給与計算の締め日も考慮に入れるとスムーズです。多くの企業では「月末締め、翌月25日払い」のように給与計算のサイクルが決まっています。
退職日を給与の締め日に合わせることで、給与計算がシンプルになり、経理担当者の手間を減らすことができます。これにより、最後の給与や退職金の支払いがスムーズに行われる可能性が高まります。
月の途中で退職する場合、日割り計算が必要となり、計算が複雑になります。会社によっては、締め日での退職を推奨されることもあります。円満退職を目指す上では、こうした会社側の事務処理の都合に配慮することも一つのポイントです。
ただし、社会保険料の負担などを考慮すると、締め日よりも月末日を優先する方が経済的なメリットは大きい場合が多いです。
ボーナス受給後に退職する際の注意点3選

ボーナスを受け取ってから退職することは、経済的なメリットが大きく魅力的ですが、いくつかの注意点があります。これらを無視すると、ボーナスが減額されたり、最悪の場合は支給されなかったりするリスクがあります。また、円満退職を目指す上でも、周囲への配慮が求められます。
具体的には、ボーナスの支給条件である「支給日在籍要件」の確認、退職意思を伝えるタイミング、就業規則の詳細な確認、そして稀なケースですがボーナス返還規定の有無の4点です。これらを事前にしっかりと把握し、計画的に行動することが重要です。
【注意点1】ボーナス支給日に在籍している必要がある
ボーナスを確実に受け取るための最も基本的な条件は、会社の定める「支給日」に在籍していることです。多くの企業では、就業規則や賃金規定において「賞与は支給日に在籍する従業員を対象とする」と明記されています。
たとえ査定期間中にどれだけ高い評価を得ていたとしても、支給日の前日に退職してしまえば、原則としてボーナスを受け取る権利を失います。有給休暇の消化期間中であっても、退職日が支給日以降であれば在籍していることになるため、支給対象となります。
まずは自社の就業規則を正確に確認し、ボーナス支給日を把握した上で、退職日をその日以降に設定することが不可欠です。
【注意点2】退職意思の伝達タイミング
ボーナス受給後に円満退職を目指す場合、退職の意思を伝えるタイミングには細心の注意が必要です。法的にはボーナスを受け取った後に退職しても何ら問題はありませんが、周囲からの心証は考慮すべき点です。
ボーナス支給直後に退職を切り出すと、「ボーナスをもらうことだけが目的だった」と受け取られ、上司や同僚との関係が悪化する可能性があります。理想的なのは、ボーナス支給後、数週間から1カ月程度の期間を空けてから退職の相談をすることです。
また、ボーナス支給前に退職の意思を伝えると、査定に影響し、支給額が減額される可能性も否定できません。会社の文化や上司との関係性にもよりますが、金銭的なメリットを最大化しつつ円満退職を目指すなら、ボーナスを受け取った後に、少し時間を置いてから伝えるのが最も無難な選択と言えるでしょう。
【注意点3】就業規則で定められた支給条件の確認
ボーナスを確実に受け取るためには、就業規則や賃金規定に定められた支給条件を事前に詳細に確認することが不可欠です。「支給日に在籍していること」が一般的な条件ですが、企業によってはさらに細かい規定が設けられている場合があります。
例えば、「賞与支給月の末日まで在籍していること」や、「支給後〇カ月以内に退職した場合は、一部を返還する」といった独自のルールが存在する可能性もゼロではありません。また、査定期間中に退職の意思を表明した場合に、査定評価を下げて支給額を減額する運用を行っている企業もあります。
無用なトラブルを避けるためには、まず自社のルールを正確に把握することが第一歩です。就業規則は従業員が閲覧できる場所に保管されているはずなので、必ず目を通しておきましょう。
税金面で慌てない退職月の選び方3選

退職する月によって、税金(住民税や所得税)の支払い方法や手続きが大きく変わります。特に、年末調整や住民税の一括徴収の仕組みを理解しておくことは、予期せぬ出費を避け、スムーズな手続きを行うために不可欠です。
ここでは、税金面で慌てないための退職月の選び方を3つのポイントに絞って解説します。12月末までの退職、1月~5月の退職、そして確定申告が必要になるケースについて、それぞれの注意点を把握し、ご自身の状況に最適なタイミングを見つけましょう。
【税金対策1】12月末までに退職すれば年末調整が完結する
所得税の観点から見ると、12月末の退職は手続きが最もシンプルで有利な選択肢です。12月31日時点で会社に在籍していれば、その年の1月から12月までの給与所得に対する年末調整を会社が行ってくれます。年末調整とは、毎月の給与から天引きされた源泉所得税の年間合計額と、本来納めるべき年間の所得税額との差額を精算する手続きです。
もし年の途中で退職し、その年内に再就職しなかった場合、この年末調整が行われないため、翌年に自身で確定申告を行う必要が生じます。確定申告は手続きが煩雑なため、12月末まで在籍して会社に年末調整を済ませてもらうことで、この手間を完全に省くことができます。
【税金対策2】1月~5月退職は住民税の一括徴収に注意
住民税の支払いに関して、1月から5月の間に退職する場合は特に注意が必要です。住民税は前年の所得に基づいて計算され、その年の6月から翌年5月までの12回に分けて給与から天引きされます。
もし1月1日から5月31日までの間に退職すると、その年の5月までに支払う予定だった残りの住民税全額が、最後の給与または退職金から一括で徴収されるのが原則です。
例えば、2月に退職する場合、2月、3月、4月、5月の4カ月分の住民税がまとめて差し引かれます。
これにより、最後の給与の手取り額が想定よりも大幅に少なくなる可能性があります。退職後の生活設計に影響が出ないよう、この時期に退職を予定している場合は、事前に自身の住民税額を確認し、一括徴収に備えておくことが重要です。
【税金対策3】退職後の確定申告が必要なケース
年の途中で退職し、その年の12月31日までに再就職しなかった場合、所得税の精算が未完了の状態となるため、原則として翌年に自身で確定申告を行う必要があります。
会社員の場合、毎月の給与から所得税が源泉徴収されていますが、これはあくまで概算額です。年末調整によって生命保険料控除や住宅ローン控除などが適用され、最終的な税額が確定しますが、年の途中で退職するとこの手続きが行われません。
確定申告を行うことで、払い過ぎた所得税が還付される可能性があります。退職時に会社から受け取る「源泉徴収票」は確定申告に必須の書類なので、必ず保管しておきましょう。手続きが面倒に感じるかもしれませんが、税金の還付を受けられるメリットがあるため、忘れずに行うことが重要です。
転職活動を考慮した退職時期の決め方4選

退職のタイミングは、転職活動の成功率にも大きく影響します。転職市場の動向を理解し、戦略的に退職時期を設定することで、より有利に活動を進めることが可能です。
求人が増える時期を狙うこと、内定から逆算してスケジュールを立てること、可能な限り在職中に活動すること、そしてキャリアの空白期間を最小限に抑えること。この4つのポイントが、スムーズなキャリアチェンジを実現するための鍵となります。それぞれのポイントを詳しく見ていきましょう。
【決め方1】求人が増える時期(3月・9月)を狙う
転職活動を有利に進めるためには、求人数が増加する時期を狙うのが効果的です。一般的に、中途採用の求人は年度末を控えた1月~3月と、下半期が始まる前の8月~9月に増える傾向があります。
1月~3月は、4月の新年度開始に向けた組織体制の構築や、冬のボーナスを受け取って退職する人の後任補充のために採用が活発化します。同様に、8月~9月は10月からの下半期に向けた人員強化や、夏のボーナス後の退職者補充が目的です。
これらの時期に転職活動を合わせることで、より多くの求人の中から自分の希望に合った企業を選ぶことができ、選択肢が広がります。退職時期をこれらの求人増加時期から逆算して設定することで、効率的な転職活動が可能になります。
【決め方2】内定から入社までの期間を逆算する
転職活動を計画的に進めるためには、内定を得てから実際に入社するまでの期間を考慮して、全体のスケジュールを逆算することが重要です。一般的に、企業が内定を出してから入社まで待ってくれる期間は、1カ月から2カ月程度が目安です。
この期間内に、現在の職場の上司に退職の意思を伝え、業務の引き継ぎを完了させ、有給休暇を消化する必要があります。例えば、引き継ぎに1カ月、有給消化に2週間かかると想定する場合、内定が出た時点で、退職日は約1.5カ月後以降に設定する必要があります。
この逆算ができていないと、転職先に無理な入社日を伝えたり、現職に迷惑をかけたりする事態になりかねません。内定を獲得した段階で、現職の就業規則や引き継ぎに必要な期間を冷静に判断し、無理のない退職スケジュールを立てましょう。
【決め方3】在職中に転職活動を進める
経済的・精神的な安定を保ちながら転職活動を行うためには、可能な限り在職中に活動を進めることが推奨されます。退職してから転職活動を始めると、収入が途絶えるため、金銭的な焦りから妥協して転職先を決めてしまうリスクが高まります。「早く決めなければ」というプレッシャーは、冷静な判断を妨げ、結果的にミスマッチな転職につながりかねません。
在職中であれば、収入が確保されているため、腰を据えて自分のキャリアプランに合った企業をじっくりと探すことができます。また、職務経歴に空白期間(ブランク)ができないため、採用担当者に「働く意欲が低いのでは」といったマイナスの印象を与える心配もありません。
仕事と両立しながらの転職活動は時間的な制約があり大変ですが、転職エージェントなどを活用すれば、効率的に進めることが可能です。
【決め方4】空白期間を最小限にする
転職活動において、職務経歴上の空白期間(ブランク)は可能な限り避けるべきです。採用担当者によっては、空白期間が長いと「働く意欲に問題があるのではないか」「計画性に欠けるのではないか」といった懸念を抱く可能性があります。
空白期間を最小限に抑える最も確実な方法は、在職中に転職活動を行い、次の職場が決まってから退職することです。理想的なのは、退職日の翌日が入社日となるようにスケジュールを調整することです。これにより、キャリアが途切れることなく、社会保険の手続きもスムーズに行えます。
やむを得ず退職後に転職活動を行う場合でも、空白期間が3カ月を超えると選考で不利になる傾向があるため、計画的に活動を進めることが重要です。もし空白期間について面接で質問された場合は、資格取得やスキルアップなど、前向きな理由を具体的に説明できるように準備しておきましょう。
女性が退職タイミングを考える際の特有のポイント3選

女性のキャリアにおいては、結婚、妊娠、出産、育児といったライフイベントが退職のタイミングを考えるうえで重要な要素となります。これらのイベントは、キャリアプランだけでなく、公的な給付金の受給資格にも大きく関わってきます。
これらのライフイベントとキャリアを両立させるためには、制度を正しく理解し、計画的に退職時期を検討することが不可欠です。ここでは、女性が退職タイミングを考える際に特に注意すべき3つのポイントについて解説します。
【女性特有のポイント1】結婚・妊娠・出産のライフイベントとの調整
結婚や妊娠、出産は、女性のキャリアにおける大きな転機です。これらのライフイベントを機に退職を考える場合、パートナーとの将来設計や家計の状況を十分に話し合い、計画的に進めることが重要です。
例えば、結婚を機に転居が必要になる場合は、転居先の地域での転職市場の状況を事前にリサーチしておく必要があります。また、妊娠・出産を考えている場合は、産前産後休業や育児休業給付金の受給要件を確認し、退職時期が受給資格に影響しないかを慎重に判断しなければなりません。
これらのライフイベントはプライベートな事柄ですが、円満退職のためには、業務の引き継ぎなどを考慮し、できるだけ早めに上司に相談することが望ましいです。ただし、伝えるタイミングや内容は、職場の雰囲気や上司との関係性に応じて慎重に判断しましょう。
【女性特有のポイント2】育児休業給付金の受給要件
育児休業給付金は、育児休業中に受け取れる非常に重要なお金です。この給付金を受給するためには、いくつかの要件を満たす必要がありますが、特に重要なのが「育児休業を開始した日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12カ月以上あること」です。
また、大前提として「育児休業後に職場復帰する予定であること」が受給の条件となっています。そのため、育児休業を取得する前提で退職を予定している場合、原則として育児休業給付金は受給できません。
ただし、当初は復帰する予定だったにもかかわらず、やむを得ない事情で育児休業中に退職せざるを得なくなった場合は、離職日(雇用保険被保険者資格の喪失日の前日)まで給付金が支給されます。出産や育児を機にキャリアプランを見直す際は、これらの公的制度の受給要件を正確に理解し、退職のタイミングが不利に働かないよう慎重に計画することが不可欠です。
【女性特有のポイント3】産休・育休取得後の退職タイミング
産休・育休を取得した後に退職を検討する場合、そのタイミングは慎重に判断する必要があります。前述の通り、育児休業給付金は職場復帰を前提としているため、育休終了後すぐに退職すると、会社との間でトラブルに発展する可能性があります。
円満退職を目指すのであれば、育休から復帰後、ある程度の期間は勤務し、業務の引き継ぎなどを誠実に行うことが望ましいです。復帰後すぐに退職せざるを得ないやむを得ない事情がある場合は、その理由を丁寧に説明し、会社の理解を得る努力が求められます。
また、育休後に退職した場合でも、働く意思と能力があり、一定の条件を満たせば失業保険(雇用保険の基本手当)を受給できる可能性があります。
退職後の経済的な基盤を確保するためにも、これらの制度について事前にハローワークなどで確認しておくことが重要です。
新卒・第二新卒が退職を検討する際の適切な時期3選

新卒や第二新卒といった若手社員が退職を考える際には、その後のキャリア形成に与える影響を十分に考慮する必要があります。早期離職は、転職市場において不利に働く可能性もゼロではありません。
しかし、適切なタイミングを見極めることで、キャリアへのダメージを最小限に抑え、次のステップへと繋げることも可能です。ここでは、新卒・第二新卒が退職を検討する上で、比較的リスクが少なく、次のキャリアに繋がりやすい3つのタイミングについて解説します。
【新卒・第二新卒の退職時期1】入社1年目の3月末:年度の区切りで退職しやすい
新卒で入社した会社が合わないと感じた場合、入社1年目の3月末は退職を検討する一つの区切りとなります。年度末であるため、会社としても新年度に向けた体制変更の時期であり、退職を受け入れやすい傾向があります。1年間勤務したという事実は、短期間での離職というマイナスイメージを多少なりとも和らげる効果が期待できます。
ただし、1年未満での退職は、転職活動において「忍耐力がない」「すぐに辞めてしまうのでは」という懸念を持たれやすいのも事実です。そのため、退職理由を明確にし、「なぜこの会社ではダメだったのか」「次の会社で何を成し遂げたいのか」を論理的に説明できる準備が不可欠です。安易な決断ではなく、熟考の末のキャリアチェンジであることを示すことが重要になります。
【新卒・第二新卒の退職時期2】入社2~3年目:第二新卒として転職市場で評価される
入社後2~3年目のタイミングは、「第二新卒」として転職市場で非常に高く評価される時期です。第二新卒とは、一般的に新卒で入社後、3年以内に離職した若手求職者を指します。企業にとって第二新卒は、基本的なビジネスマナーや社会人としての基礎体力が身についている一方で、まだ特定企業の文化に染まりきっていないため、新しい環境への順応性が高いと期待されます。
ポテンシャルを重視した採用枠が多いため、未経験の職種や業界へキャリアチェンジする絶好の機会でもあります。2~3年の実務経験は、自身の適性を見極め、次のキャリアを考える上で十分な期間です。
この時期に、現職で得たスキルや経験を棚卸しし、明確な目的意識を持って転職活動に臨むことで、キャリアアップを実現しやすくなります。
【新卒・第二新卒の退職時期3】試用期間終了後:正社員として実績を積んでから退職
試用期間は、従業員がその職務に適しているかを会社が判断する期間であると同時に、従業員自身が会社を見極める期間でもあります。この期間中に「どうしても合わない」と感じた場合、試用期間満了をもって退職するという選択肢もあります。
一方で、試用期間中の退職は職歴として非常に短く、転職活動で不利になる可能性が極めて高いです。そのため、可能であれば試用期間を終え、正社員として少なくとも1年程度は勤務し、何らかの実績やスキルを身につけてから退職を検討するのが賢明です。
正社員としての勤務経験は、責任感や業務遂行能力の証明となります。たとえ短い期間であっても、具体的な業務内容や成果を職務経歴書に記載できれば、採用担当者へのアピール材料になります。一時的な感情で判断せず、少しでもキャリアにプラスになる経験を積むことを目指しましょう。
円満退職を実現するための退職手続きの流れ5ステップ

円満退職は、次のキャリアへ気持ちよく進むために、そしてこれまでお世話になった会社への礼儀として非常に重要です。感情的になったり、手続きを疎かにしたりすると、思わぬトラブルに発展しかねません。
ここでは、円満退職を実現するための基本的な流れを5つのステップに分けて解説します。適切なタイミングで上司に意思を伝え、必要な書類を提出し、責任を持って引き継ぎを行う。この一連のプロセスを丁寧に進めることが、良好な関係を保ったまま退職する鍵となります。
【ステップ1】退職の意思を直属の上司に伝える(退職希望日の1~3カ月前)
円満退職の第一歩は、退職の意思をまず直属の上司に伝えることです。人事部や他の同僚に先に話すのはマナー違反とされ、上司との信頼関係を損ねる行為と受け取られかねません。
伝えるタイミングは、会社の就業規則を確認した上で、一般的には退職希望日の1カ月から3カ月前が目安です。これにより、会社側は後任者の選定や業務の引き継ぎ計画を立てるための十分な時間を確保できます。
伝える際は、「ご相談したいことがあります」と事前にアポイントを取り、会議室など他の人に聞かれない場所で、直接対面で話すのが基本です。退職理由は、たとえ不満があったとしても、「新しい分野に挑戦したい」など、ポジティブな表現で伝えることが、スムーズな話し合いにつながります。
【ステップ2】退職届を提出する
上司との話し合いで退職日について合意が得られたら、会社の規定に従って正式な「退職届」を提出します。口頭での合意だけでなく、書面で意思表示を行うことで、退職の事実を明確にし、後のトラブルを防ぐ役割があります。
会社によっては所定のフォーマットが用意されている場合がありますが、ない場合は自分で作成します。退職届には、退職理由(自己都合の場合は「一身上の都合により」と記載)、退職日、提出日、所属部署、氏名を記入し、捺印します。
提出先は、就業規則に定められている通り、直属の上司または人事部に提出します。退職願は「退職のお願い」であり撤回できるのに対し、退職届は「退職の確定通知」であり、原則として撤回できないという違いがあることも理解しておきましょう。
【ステップ3】業務の引き継ぎを計画的に進める
円満退職において、業務の引き継ぎは最も重要なプロセスです。自分が退職した後も業務が滞りなく進むよう、後任者や関係者に責任を持って業務内容を伝える必要があります。
まずは、自分が担当している業務をすべて洗い出し、リスト化します。そして、後任者が決まったら、そのリストに基づいて引き継ぎのスケジュールを立て、計画的に進めましょう。口頭での説明だけでなく、業務マニュアルや手順書などの資料を作成しておくと、後任者が後から確認できるため非常に親切です。
取引先への挨拶や後任者の紹介も、引き継ぎの一環として忘れずに行いましょう。最終出社日までにすべての引き継ぎが完了するよう、余裕を持ったスケジュールを組むことが、社会人としての最低限のマナーです。
【ステップ4】有給休暇の消化スケジュールを調整する
退職日までに残っている有給休暇を消化することは、労働者に認められた正当な権利です。円満退職を目指すうえでは、業務の引き継ぎに支障が出ないよう、計画的に消化することが重要になります。
まずは、自身の有給休暇の残日数を確認します。そのうえで、引き継ぎに必要な期間を考慮し、最終出勤日と退職日(有給消化最終日)を決定します。このスケジュールについては、退職の意思を伝える際に上司に相談し、了承を得ておくとスムーズです。
繁忙期を避けたり、引き継ぎを前倒しで進めたりするなど、会社への配慮を示すことで、有給消化への理解も得やすくなります。権利だからと一方的に取得するのではなく、周囲と調整しながら進める姿勢が、良好な関係を保ったまま退職する秘訣です。
【ステップ5】退職日に必要書類を受け取る
最終出勤日または退職日には、会社から貸与されていた物品を返却し、同時に退職後の手続きに必要な重要書類を受け取ります。これらの書類は、失業保険の申請や転職先での手続きに不可欠なため、漏れなく受け取ったか必ず確認しましょう。
- 健康保険被保険者証(保険証)
- 社員証、IDカード、名刺
- 会社の経費で購入した備品(PC、携帯電話など)
- 離職票:失業保険の受給手続きに必要
- 雇用保険被保険者証:転職先に提出が必要
- 源泉徴収票:確定申告や転職先での年末調整に必要
- 年金手帳:国民年金への切り替えや転職先に提出が必要
これらの書類は、退職後すぐに発行されず、後日郵送される場合も多いです。いつ頃受け取れるのかを事前に人事担当者に確認しておくと、その後の手続きをスムーズに進めることができます。
まとめ
仕事を辞める最適なタイミングは、個人の状況や目的によって異なります。
本記事で解説した通り、ボーナス、税金、社会保険、転職市場の動向などを総合的に考慮し、計画的に退職日を設定することが重要です。
特に、経済的な損失を避けるためには、ボーナス支給日後の月末や、年末調整が完了する12月末などが有利な選択肢となります。また、転職活動をスムーズに進めるためには、求人が増える3月や9月を見据えて行動を起こすのが効果的です。
円満退職を実現するためには、余裕を持ったスケジュールで上司に意思を伝え、責任を持って引き継ぎを行うことが不可欠です。
退職は次のキャリアへの第一歩です。
この記事を参考に、あなたにとって最も有利なタイミングを見極め、後悔のない選択をしてください。
今の会社、ちょっと"モヤモヤ"してませんか?
あなたの"会社不満度"をスコア化して、
次のキャリアの可能性をチェック!
よくある質問
退職日は月末と月初のどちらがお得ですか?
社会保険料の観点から、転職先が決まっていない場合は月末退職が有利です。社会保険料は月末時点の在籍企業で支払われるため、月末に退職すればその月の保険料は会社が半額負担します。月初に退職すると、その月の国民健康保険料と国民年金保険料を自身で全額支払う必要が生じます。
ボーナスをもらってすぐ退職するのは問題ありませんか?
法的には問題ありませんが、円満退職を目指すなら配慮が必要です。ボーナス支給直後の退職は「ボーナス目当て」と見なされ、上司や同僚の心証を損なう可能性があります。可能であれば、支給後数週間から1カ月程度は期間を空け、その間に引き継ぎを誠実に行うことで、周囲の理解を得やすくなります。
退職後の住民税はどのように支払いますか?
退職時期によって異なります。1月~5月に退職した場合は、5月までの残りの住民税が最後の給与から一括で天引きされるのが一般的です。
一方で、6月~12月に退職した場合、退職月分のみを給与から天引きし、翌月以降の分は自分で納付するか、あるいは退職月に翌年5月分までを一括で天引きする、という方法になります。 なお、退職後すぐに転職する際は、退職月分だけが天引きされ、翌月からは新しい勤務先で徴収が引き継がれます。 支払い方法にはこうした違いがあるため、いつ退職するかを検討する材料にしてください。
有給休暇を消化してから退職できますか?
はい、有給休暇の取得は労働者の権利であり、退職前にすべて消化することが可能です。円満に退職するためには、業務の引き継ぎに支障が出ないよう、事前に上司と相談し、計画的に消化スケジュールを立てることが重要です。退職の意思を伝える際に、有給消化の希望も合わせて伝えることで、スムーズな調整がしやすくなります。
退職を伝えるタイミングはいつが適切ですか?
一般的には、退職希望日の1カ月から3カ月前に直属の上司に伝えるのがベストです。会社の就業規則に「退職の申し出は〇カ月前まで」といった規定がある場合は、それに従うのが基本です。早めに伝えることで、会社側も後任者の選定や引き継ぎの準備を余裕を持って進めることができ、円満退職につながりやすくなります。