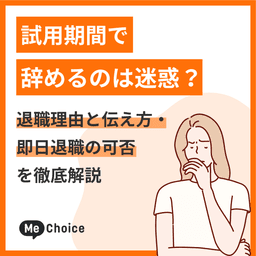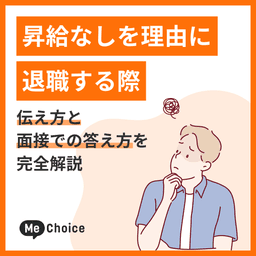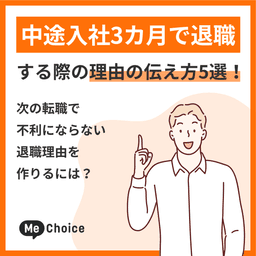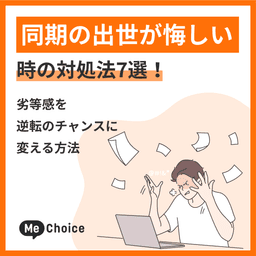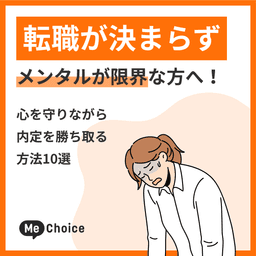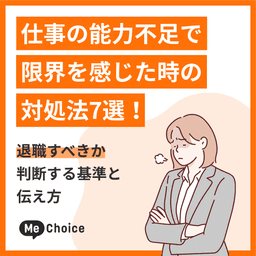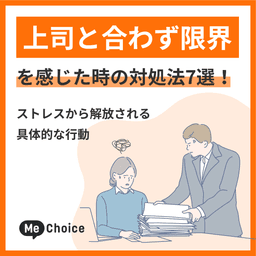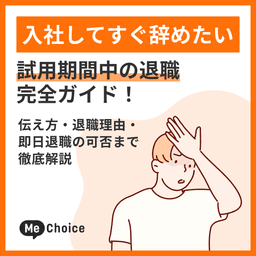

試用期間中の退職が多い理由と円満に辞めるための完全ガイド
試用期間中に「この会社、自分には合わないかもしれない……」と退職を考えたことはありませんか?」
新しい環境への期待とは裏腹に、現実とのギャップに戸惑うことは少なくありません。
この記事を読めば、試用期間中に退職する人が多い理由から、円満に辞めるための具体的な手順、そして次のキャリアに繋げるためのポイントまで全てわかります。
以下の内容についてご紹介します。
- 試用期間中に退職する人が多い5つの理由
- 円満に退職するための具体的な手順と伝え方
- 短期離職を次のキャリアに活かすための対策
次のステップに不安がある方は、転職エージェントに相談してみるのも一つの有効な手段です。
今の会社、ちょっと"モヤモヤ"してませんか?
あなたの"会社不満度"をスコア化して、
次のキャリアの可能性をチェック!
1試用期間中に退職する人が多い理由5選

試用期間中に退職する人が多い主な原因は、入社前に抱いていた期待と入社後の現実との間に生じる「ミスマッチ」です。
具体的には、業務内容、職場の人間関係、労働条件など、さまざまな面でギャップを感じることが早期離職の引き金となります。
このミスマッチは、求職者側の企業研究不足だけでなく、企業側の採用プロセスや受け入れ体制における課題を示唆している場合も少なくありません。ここでは、特に多く見られる5つの退職理由について詳しく解説します。
1-1【退職理由1】入社前の想像と実際の業務内容にギャップがあった
求人情報や面接で説明された業務内容と、入社後に実際に任される仕事が大きく異なることは、早期退職の典型的な理由の一つです。
例えば、「企画職」として採用されたにもかかわらず、実際には雑務ばかりを任されたり、「裁量権を持って働ける」と聞いていたのに、実際には細かな指示のもとでしか動けなかったりするケースが挙げられます。
このような状況は、仕事に対するモチベーションの低下を招き、自身のキャリアプランとのズレを感じさせる大きな原因となります。
業務内容のギャップは、職種そのものが異なるというさらに深刻なケースもあります。例えば、「データ入力の事務職」として入社したはずが、実際には「飛び込み営業」を命じられるといった事例です。これは単なる認識の違いではなく、企業側の説明責任に関わる問題であり、労働者の信頼を著しく損なう行為と言えるでしょう。
1-2【退職理由2】職場の人間関係や社風が合わなかった
職場の雰囲気や人間関係が、入社前に想像していたものと合わないことも、大きな退職理由となります。
例えば、高圧的な態度を取る上司がいる、いわゆるパワハラが横行している環境や、質問しづらい雰囲気で円滑なコミュニケーションが取れない職場では、従業員は大きな精神的ストレスを抱えることになります。また、十分な研修や指導がなく、入社後すぐに放置されてしまうケースも、孤立感や不安を増大させ、早期離職につながります。
社風とのミスマッチは、挨拶が交わされないといった日常的な光景からも感じ取れることがあります。挨拶はコミュニケーションの基本ですが、これが欠如している職場は、チームワークや相互尊重の文化が根付いていない可能性があります。このような環境は、従業員のエンゲージメントを低下させ、心身の健康を守るために退職を選択する一因となります。
1-3【退職理由3】労働条件(残業時間・給与など)が求人情報と異なっていた
給与や労働時間といった、事前に提示された労働条件と実際が異なるケースは、生活に直接影響するため、退職の大きな引き金となります。
例えば、「残業はほとんどない」と説明されていたにもかかわらず、入社してみると長時間労働が常態化している、あるいは求人票に記載されていた手当が給与に含まれていないといった状況です。このような食い違いは、会社に対する不信感を増大させ、早期退職を決意させる直接的な原因となります。
労働条件のミスマッチは、単なるギャップにとどまらず、労働基準法に抵触する問題を含むこともあります。具体的には、残業代が支払われない「サービス残業」の強要、法律で定められた休憩時間が与えられない、有給休暇の取得を認めないといったケースです。これらは明らかな法令違反であり、従業員の権利を侵害する行為であるため、試用期間中であっても退職を検討すべき正当な理由と言えます。
1-4【退職理由4】精神的・身体的な負担が想像以上に大きかった
新しい環境での業務は、誰にとってもある程度のストレスが伴いますが、その負担が心身の健康を脅かすレベルに達することもあります。
例えば、過度な残業や休日出勤が続くことで慢性的な疲労や不眠に陥ったり、職場の人間関係によるストレスで出社時に強い不安を感じたりするケースです。このような状態は、慢性的な疲労が取れず、不眠や常に不安を感じるといった心身の健康を損ねるリスクもはらんでいます。
特に、試用期間中はまだ業務に慣れていないため、プレッシャーを感じやすい時期です。しかし、その負担が自身の許容量を明らかに超えていると感じる場合は、無理に働き続ける必要はありません。自身の健康を最優先に考え、早期に環境を変えるという決断も重要です。
1-5【退職理由5】能力不足を感じ、業務についていけなかった
試用期間中は新しい業務を覚える段階であり、誰もが最初はうまくいかないものです。しかし、周囲の期待と自身のスキルとの間に大きな隔たりを感じ、「このままでは会社に貢献できない」とプレッシャーを感じてしまうことがあります。
会社側は、新入社員がすぐに完璧なパフォーマンスを発揮するとは期待していません。むしろ、仕事に対する姿勢や学習意欲を評価しています。しかし、本人にとっては、日々の業務についていけないという事実が大きな負担となり、自信を喪失してしまうことがあります。
このような能力不足による退職は、必ずしもネガティブなことばかりではありません。この経験を通じて、自身の得意なことや苦手なことを客観的に把握し、より適性のある職種や業界を見つけるきっかけになることもあります。重要なのは、衝動的に判断せず、一度立ち止まって自身のキャリアを冷静に見つめ直すことです。
2試用期間中に退職するデメリット3選

試用期間中の退職は、合わない環境から早期に抜け出せるメリットがある一方で、いくつかのデメリットも存在します。特に、将来のキャリアに与える影響については、決断を下す前に冷静に理解しておくことが重要です。ここでは、主な3つのデメリットについて解説します。
2-1【デメリット1】転職活動で不利になる可能性がある
試用期間中という短期間での離職歴は、次の転職活動において採用担当者に慎重な印象を与える可能性があります。採用する企業は、採用と教育にコストをかけているため、長く貢献してくれる人材を求めています。そのため、「またすぐに辞めてしまうのではないか」という懸念を抱かれやすいのです。
このデメリットを乗り越えるためには、面接で退職理由を問われた際に、採用担当者が納得できるような説明が不可欠です。単に「合わなかった」と伝えるのではなく、その経験から何を学び、次にどう活かしたいのかを前向きかつ論理的に語れるように準備しておく必要があります。短期離職の事実を隠すことはできず、むしろ誠実に向き合う姿勢が求められます。
2-2【デメリット2】短期離職の経歴が履歴書に残る
試用期間中であっても、一度雇用契約を結んだ以上、その経歴は職歴として残ります。たとえ数週間や1カ月といった短期間であっても、履歴書に記載するのが原則です。
この「短期離職」の記録は、応募書類の中で必ず目につく項目となります。採用担当者は、この記録を見て「なぜ短期間で辞めたのか」という疑問を持つため、面接ではその理由について深掘りされることを覚悟しなければなりません。
もし、この事実を隠して履歴書に記載しなかった場合、あとから雇用保険の加入履歴などで発覚すると「経歴詐称」と見なされ、信頼を大きく損なう可能性があります。最悪の場合、内定取り消しや懲戒解雇につながるリスクもあるため、正直に記載することが不可欠です。
2-3【デメリット3】雇用保険の失業給付を受けられない場合がある
試用期間中のように在籍期間が短い自己都合退職の場合、雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険)を受給できない可能性が高いです。
失業保険を受給するには、原則として「離職日以前2年間に、被保険者期間が通算して12カ月以上あること」が必要です。試用期間のみの勤務では、この条件を満たすことは通常困難です。
ただし、前職の被保険者期間と合算できる場合や、会社の倒産・解雇といった特定の理由に該当する場合は、受給要件が緩和されることもあります。
いずれにせよ、退職後にすぐ次の仕事が決まらない場合、収入が途絶えるリスクを十分に認識しておく必要があります。退職を決断する前に、自身の資産状況を確認し、生活費の計画を立てておくことが賢明です。
3試用期間中の退職を円満に進める手順5ステップ

試用期間中に退職を決意した場合、感情的にならず、社会人としてのマナーを守って手続きを進めることが、円満退職の鍵となります。会社に与える影響を最小限に抑え、スムーズに次のステップへ進むための具体的な手順を5つのステップで解説します。
3-1【手順1】退職の意思を直属の上司に口頭で伝える
退職を決意したら、まず直属の上司に口頭でその意思を伝えるのが最初のステップです。
同僚や人事担当者に先に話すのではなく、指揮命令系統のトップである直属の上司に最初に伝えるのが社会人としてのマナーです。
伝える際は、「ご相談したいことがあります」と事前にアポイントを取り、他の人がいない会議室などで一対一で話せる場を設けるのが理想的です。これにより、落ち着いて話を進めることができ、周囲への配慮も示すことができます。
法律上は退職日の2週間前までに伝えればよいとされていますが、会社の就業規則に「1カ月前まで」などの規定がある場合は、可能な限りそれに従う姿勢を見せることで、より円満な退職につながります。
3-2【手順2】退職理由を簡潔かつ前向きに説明する
上司に退職の意思を伝える際は、理由を正直かつ簡潔に説明することが重要です。会社の批判や不満を並べ立てるのではなく、あくまで「一身上の都合」として、自身のキャリアプランや適性を理由にすることが円満退職のポイントです。
例えば、「実際に業務に携わる中で、自身の適性や将来目指したいキャリアの方向性を改めて考えた結果、別の道に進む決意をいたしました」といったように、前向きな決断であることを伝えましょう。
たとえネガティブな理由があったとしても、それをストレートに伝えることは避け、相手への配慮を忘れない姿勢が大切です。感謝の気持ちを添えることで、より良い関係性を保ったまま話を進めることができます。
3-3【手順3】退職届を作成し、人事担当者に提出する
上司との話し合いで退職の合意が得られたら、正式な手続きとして退職届を提出します。退職届は、退職の意思を明確な証拠として書面に残すための重要な書類です。これにより、後の「言った・言わない」といったトラブルを防ぐことができます。
退職届には、以下の項目を明記するのが一般的です。
- 退職の意思表明
- 退職日
- 提出日
- 所属部署
- 氏名
退職理由は「一身上の都合」と記載するのが通例です。押印は法律上の必須要件ではありませんが、会社の規定や慣例で求められることが多いため、社内ルールに従うのが賢明です。提出先は、上司の指示に従い、人事部などに直接、または上司経由で提出します。
3-4【手順4】引き継ぎ業務を誠実に行う
試用期間中であっても、担当していた業務が少しでもあれば、後任者や他の従業員への引き継ぎを誠実に行う責任があります。短期間であっても、関わったプロジェクトの進捗状況や、やり取りのあった顧客情報など、必要な情報を漏れなく共有することが、会社への最後の貢献であり、社会人としてのマナーです。
引き継ぎ資料を作成したり、後任者とミーティングの時間を設けたりするなど、会社に迷惑がかからないよう最大限の配慮をしましょう。この姿勢は、円満な退職に不可欠であり、万が一、将来どこかで仕事上の関わりが生まれた際にも、良好な関係を保つための土台となります。
3-5【手順5】退職日まで欠勤せず、最後まで責任を持って勤務する
退職の意思を伝え、退職日が確定した後も、最終出社日までは会社の従業員であることに変わりはありません。無断欠勤などはせず、最後まで責任を持って勤務することが重要です。
もし有給休暇が残っている場合は、上司と相談の上、引き継ぎに支障のない範囲で消化することも可能です。
最終日には、お世話になった上司や同僚に挨拶をし、感謝の気持ちを伝えましょう。また、パソコンや社員証、制服といった会社からの貸与品は、すべて返却します。返却漏れがないか、事前にリストアップして確認すると確実です。
最後まで誠実な態度で勤務を全うすることが、円満な退職の締めくくりとなります。
4試用期間中の退職で気まずさを軽減する伝え方3つのポイント

試用期間中に退職を申し出るのは、誰にとっても気まずいものです。しかし、伝え方を少し工夫するだけで、相手に与える印象は大きく変わり、円満な退職につながります。ここでは、気まずさを和らげ、スムーズに話を進めるための3つの重要なポイントを解説します。
4-1【ポイント1】退職理由は「自己都合」を基本とし、会社批判は避ける
退職理由を伝える際は、たとえ会社に不満があったとしても、それを直接的な批判として表現するのは避けましょう。「人間関係が悪い」「給料が低い」といったネガティブな理由をストレートに伝えると、相手を不快にさせ、感情的な対立を生む可能性があります。
円満に退職するためには、あくまで「自己都合」という形を取ることが重要です。「自身のキャリアプランを考えた結果」や「自分の適性と業務内容に相違があった」など、自分自身の問題として理由を説明することで、相手も受け入れやすくなります。
会社や特定の個人を責めるような言い方を避け、自分の将来を見据えた前向きな決断であることを強調するのが、気まずさを軽減するコツです。
4-2【ポイント2】感謝の気持ちを必ず伝える
たとえ短い期間であったとしても、採用してくれたことや、業務について指導してくれたことへの感謝の気持ちを伝えることは、円満な退職において非常に重要です。
退職の話を切り出す際や、話の最後に「短い間でしたが、大変お世話になりました。多くのことを学ばせていただき、感謝しております」といった言葉を添えるだけで、相手の心証は大きく変わります。
感謝の言葉は、あなたが会社に対して敬意を払っていることを示すものです。これにより、退職というネガティブな話題であっても、建設的な話し合いの雰囲気を保ちやすくなります。退職理由がどのようなものであれ、お世話になった事実に対して感謝を伝える姿勢を忘れないようにしましょう。
4-3【ポイント3】退職日までの業務に対する誠意を示す
退職の意思を伝えた後も、最終出社日までは従業員としての責任があります。「どうせ辞めるから」という態度ではなく、引き継ぎや残りの業務に対して誠実に取り組む姿勢を見せることが、信頼を損なわないために不可欠です。
「退職日までは、ご迷惑をおかけしないよう、責任を持って業務の引き継ぎを行います」といった言葉を添えることで、あなたの誠意が伝わります。
実際に、後任者が困らないように分かりやすい資料を作成したり、丁寧な説明を心がけたりする行動は、会社への最後の貢献となります。この誠実な態度は、たとえ退職する身であっても、社会人としての評価を高め、気まずい雰囲気を和らげる効果があります。
5試用期間中に即日退職したい場合の対処法2選

「もう一日も会社に行きたくない」という状況で、試用期間中に即日退職を希望するケースもあります。しかし、原則として即日退職は簡単ではありません。法律上のルールを理解し、適切な手順を踏むことが重要です。ここでは、即日退職を検討する際の3つの対処法を解説します。
5-1【対処法1】民法627条に基づき2週間前に退職を申し出る
法律上、労働者が退職する権利は保障されていますが、即日退職が原則ではありません。民法第627条では、期間の定めのない雇用契約の場合、労働者はいつでも解約の申し入れができ、その申し入れから2週間が経過することで雇用契約が終了すると定められています。
つまり、「明日から来ません」は原則として認められず、退職の意思を伝えてから2週間は在籍する義務があるということです。この期間に有給休暇が残っていれば、それを消化して実質的に出社しないという選択肢もありますが、まずは会社と相談することが基本となります。
5-2【対処法2】体調不良など正当な理由がある場合は会社と交渉する
原則として2週間の予告期間が必要ですが、「やむを得ない事由」がある場合は、即時に契約を解除できる可能性があります。
この「やむを得ない事由」には、自身の深刻な病気や家族の介護などが該当します。また、労働基準法第15条2項では、事前に明示された労働条件と事実と相違する場合にも、労働者は即時に労働契約を解除できると定められています。
例えば、ハラスメントによって心身に不調をきたした場合(体調不良)や、求人票と全く異なる業務内容や勤務条件であった場合などがこれにあたります。これらの正当な理由がある場合は、会社と交渉することで、2週間を待たずに退職できる可能性があります。医師の診断書など、客観的な証拠があると交渉しやすくなります。
6試用期間中の退職が転職活動に与える影響と対策3選

試用期間中に退職した場合、次の転職活動でその経歴がどのように評価されるか不安に思う方も多いでしょう。短期離職は確かに懸念材料と見なされがちですが、適切な対策を講じることで、マイナスの影響を最小限に抑え、むしろ自己分析の深さを示す機会に変えることも可能です。ここでは、転職を成功させるための3つの対策を解説します。
6-1【対策1】短期離職の理由を前向きに説明できるよう準備する
面接では、試用期間中に退職した理由を必ず質問されます。このとき、前職の不満や批判を述べるのではなく、「自身の成長やキャリアプランのための前向きな決断であった」と説明することが極めて重要です。
例えば、「前職での経験を通じて、自身の強みが〇〇にあると再認識し、その強みをより活かせる環境で貢献したいと考えました」といったように、自己分析の結果と将来への意欲を結びつけて語りましょう。
「合わなかった」という一言で終わらせず、その経験から何を学び、それが今回の応募企業でどう活かせるのかを具体的に示すことで、採用担当者に納得感と熱意を伝えることができます。この準備を怠ると、「またすぐに辞めるかもしれない」という懸念を払拭できません。
6-2【対策2】次の職場選びでは企業研究を徹底する
同じ失敗を繰り返さないために、次の職場選びでは徹底した企業研究が不可欠です。
前回の退職理由が「ミスマッチ」であったなら、なぜそのミスマッチが起きたのかを分析し、次の企業選びの軸を明確にしましょう。
企業のウェブサイトや求人情報だけでなく、社員の口コミサイトやニュース記事、SNSなども活用し、社風や働き方の実態について多角的に情報を収集することが重要です。
可能であれば、カジュアル面談やOB/OG訪問などを通じて、実際に働く社員の声を聞く機会を設けるのも有効です。これにより、入社後のギャップを最小限に抑え、自分に本当に合った環境かどうかを見極めることができます。
6-3【対策3】転職エージェントを活用し、客観的なアドバイスを受ける
短期離職からの転職活動は、一人で進めることに不安を感じるかもしれません。そのような場合は、転職エージェントを有効活用することを強くおすすめします。
転職エージェントは、求人紹介だけでなく、キャリア相談のプロフェッショナルです。あなたの経歴や退職理由を客観的に分析し、どのように伝えれば採用担当者にポジティブな印象を与えられるか、具体的な面接対策を指導してくれます。
また、エージェントは企業の内部情報(社風、人間関係、残業の実態など)に精通していることが多く、求人票だけでは分からないリアルな情報を提供してくれます。これにより、次の職場でのミスマッチを防ぐことができます。無料で利用できるサービスがほとんどなので、専門家のサポートを受けながら、戦略的に転職活動を進めましょう。
7試用期間中の不調で退職を検討する際の注意点3選

試用期間中に新しい環境への適応や業務のプレッシャーから、心身に不調をきたしてしまうことは少なくありません。もし退職を考えるほどの不調を感じているなら、自身の健康を最優先に行動することが大切です。ここでは、心身の不調を理由に退職を検討する際に知っておくべき3つの注意点を解説します。
7-1【注意点1】医療機関を受診する
心身の不調が続くようなら専門の医療機関を受診しましょう。医師の診断を受けることで、自身の状態を客観的に把握できます。もし診断が下りた場合、その診断書は、休職や退職の手続きをスムーズに進めるための重要な証明となります。会社に自身の状況を正確に伝え、理解を得るためにも、専門家の判断を仰ぐことが第一歩です。
7-2【注意点2】休職制度の利用可否を会社に確認する
すぐに退職を決断する前に、会社の休職制度を利用できないか確認してみましょう。多くの企業では、病気やけがで長期間働くことが困難になった従業員のために、一定期間雇用を維持したまま休める制度を設けています。就業規則を確認するか、人事部に問い合わせてみましょう。
休職期間中に心身を休めることで、回復し、復職できる可能性もあります。また、休職中に今後のキャリアについて冷静に考える時間を持つこともできます。
ただし、試用期間中の従業員が休職制度の対象となるかどうかは、会社の規定によって異なります。まずは利用できる制度があるかを確認し、退職以外の選択肢も検討することが重要です。
7-3【注意点3】傷病手当金の受給条件を事前に把握しておく
業務外の病気やけがで働くことができなくなった場合、健康保険から傷病手当金が支給される可能性があります。これは、休業中の生活を支えるための重要な制度です。
傷病手当金を受給するには、以下の条件を満たす必要があります。
- 業務外の事由による病気やけがの療養のための休業であること
- 仕事に就くことができないこと
- 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
- 休業した期間について給与の支払いがないこと
退職後も、一定の条件を満たせば継続して受給できる場合があります。心身の不調で休職や退職を検討する際は、この制度の対象となるか、事前に健康保険組合や会社の担当者に確認しておきましょう。経済的な不安を和らげることが、療養に専念するための助けとなります。
8まとめ
試用期間中の退職は決して珍しいことではなく、入社前後のミスマッチが主な原因です。業務内容、人間関係、労働条件などに違和感を覚えた場合、早期に決断することは自分自身と企業の双方にとってメリットとなる場合があります。
退職を決意した際は、法律やマナーを守り、直属の上司に早めに相談することが円満退職の鍵です。短期離職の経験を次のキャリアに活かすためにも、退職理由を前向きに整理し、転職エージェントなどを活用して慎重に次のステップに進みましょう。
今の会社、ちょっと"モヤモヤ"してませんか?
あなたの"会社不満度"をスコア化して、
次のキャリアの可能性をチェック!
9よくある質問
試用期間中に退職すると迷惑をかけますか?
試用期間中の退職は、法的に認められた労働者の権利であり、必ずしも迷惑がかかるわけではありません。むしろ、合わない環境で働き続けるよりも早期に決断する方が、企業側も採用計画を立て直しやすく、双方にとって良い結果となる場合があります。
試用期間中の退職は履歴書に書く必要がありますか?
はい、たとえ短期間であっても職歴として履歴書に記載するのが原則です。記載しないと経歴詐称と判断されるリスクがあります。面接で理由を前向きに説明することが重要です。
試用期間中に退職届は必要ですか?
はい、必要です。退職の意思を明確な証拠として書面に残すため、退職届の提出が一般的です。まず上司に口頭で退職の意思を伝えた後、会社の規定に従って提出します。これにより、「言った・言わない」といった後のトラブルを防ぐことができます。
試用期間3日で退職することは可能ですか?
会社の合意があれば可能ですが、原則として民法に基づき2週間前の申し出が必要です。ただし、労働条件が事前に明示されたものと著しく異なる場合や、やむを得ない事由がある場合は即時退職が認められることもあります。まずは上司に相談することが重要です。
試用期間中の退職理由で「合わない」と伝えても問題ありませんか?
問題ありませんが、伝え方が重要です。「社風が合わない」といった抽象的な表現よりも、「自身のキャリアプランと業務内容に乖離を感じた」など、具体的かつ前向きな理由として説明するのが円満退職のコツです。会社批判と受け取られないよう配慮しましょう。