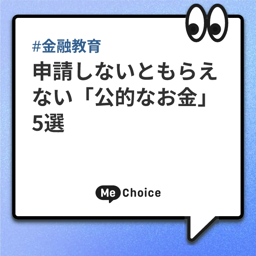
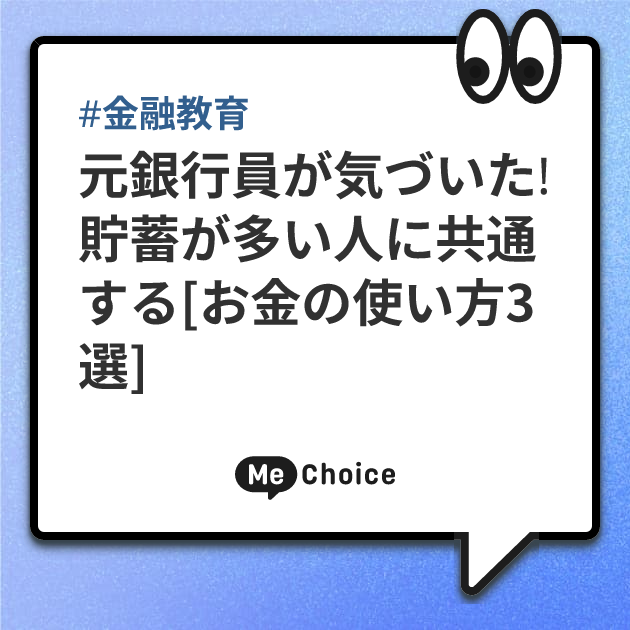
【元銀行員が気づいた】貯蓄が多い人に共通する「お金の使い方」3選。年代別の貯蓄平均・中央値つき
内閣府が2025年1月に発表した「国民生活に関する世論調査」(令和6年8月実施)では、「資産や貯蓄への満足度」に関して、およそ7割の人が不満を抱いていることがわかりました。満足していると回答した人は全体の28.6%、不満ありと答えた人は70.7%にのぼっています。
「限られた今の収入で本当に貯蓄を増やせるのか」と悩んでいる方も多いかもしれません。
ところが、貯蓄額と収入は必ずしも比例しないことがわかってきました。年収が200万円に満たない世帯でも貯蓄500万円以上を実現しているケースがある一方で、収入が多くても貯蓄がほとんどできていないという人も少なくありません。
本記事では、金融機関に勤務していた筆者が実際に出会った「貯め上手な人々」に共通していた習慣や考え方をご紹介していきます。身近な例からヒントを得て、今日から始められることを探してみましょう。
1貯蓄額は年収に比例するとは限らない
「貯蓄がたくさんある人」と「そうでない人」の違いというと、多くの人が収入の差を思い浮かべるかもしれません。
しかし、貯蓄額は必ずしも収入だけに左右されるわけではありません。
2024年9月に総務省統計局が発表した「家計調査年報(貯蓄・負債編)2023年(令和5年)」によると、二人以上の世帯のうち勤労者世帯の平均年収と貯蓄は以下の通りとなっています。
1-1年収レンジ別の平均貯蓄額(二人以上の世帯のうち勤労者世帯)
平均年収200万円未満:平均貯蓄額543万円
平均年収200万~250万円:平均貯蓄額1164万円
平均年収250万~300万円:平均貯蓄額716万円
平均年収300万~350万円:平均貯蓄額783万円
平均年収350万~400万円:平均貯蓄額827万円
平均年収400万~450万円:平均貯蓄額875万円
平均年収450万~500万円:平均貯蓄額987万円
平均年収500万~550万円:平均貯蓄額1033万円
平均年収550万~600万円:平均貯蓄額1061万円
平均年収600万~650万円:平均貯蓄額1040万円
平均年収650万~700万円:平均貯蓄額1263万円
平均年収700万~750万円:平均貯蓄額1285万円
平均年収750万~800万円:平均貯蓄額1346万円
平均年収800万~900万円:平均貯蓄額1540万円
平均年収900万~1000万円:平均貯蓄額1880万円
平均年収1000万~1250万円:平均貯蓄額2029万円
平均年収1250万~1500万円:平均貯蓄額2418万円
平均年収1500万円以上:平均貯蓄額4014万円
いかがでしょうか。
このように、平均年収が多くなるにつれて平均貯蓄額も増える傾向にはありますが、必ずしも年収が高ければびっくりするような貯蓄ができるということでもなさそうです。
1-2年収200万~250万世帯の平均貯蓄額は1164万円
平均年収200万~250万円世帯を見てみると、平均貯蓄額1164万円と突出していることがわかります。
平均年収が倍の400万~500万円世帯と比較しても、平均貯蓄額は高く、年収と貯蓄額は関係がないのではないかと思う人も多いでしょう。
貯蓄が上手な人は、年収に関わらず、ある習慣があるように感じます。
ここからは、元銀行員が今まで見てきた貯蓄上手な人の共通点についてご紹介していきます。
2元銀行員が教える!貯蓄上手な人の共通点3選
貯蓄上手な人には、実はある共通した特徴があります。
ここからは、筆者が銀行員としての経験で見た貯蓄上手な人のやりがちな行動と、その改善ポイントを紹介していきます。
2-1お金の使い方(その1):毎月の「固定貯蓄額」を先取りで確保する
収入から貯蓄や投資分を引いた残りのお金でやりくりしよう

出所:金融庁「資産形成の基本」
毎月の収入から生活費を差し引いた残りを貯金しようとすると、気づけば使い切ってしまうことも珍しくありません。
そこで効果的なのが、「先取り貯蓄」です。給料が振り込まれたら、まず一定額を貯蓄用の口座に移し、それ以外の金額で生活するという方法です。自動積立機能を活用すると、手間をかけずに習慣化することができ、貯蓄が継続しやすくなります。
貯蓄が上手な人の多くは、「余ったお金を貯金する」のではなく、「貯蓄を最優先にする」という習慣を持っています。貯蓄の目的を明確にしておくと、貯蓄のモチベーションが維持しやすくなると話していた方が多くいました。
2-2お金の使い方(その2):お金の「マイルール」を持っている
貯蓄ができる人は、お金の使い方に一貫したルールを持っていることが多いです。「何となく」お金を使ってしまうと、気づかないうちに出費が増え、貯蓄が思うように進みません。
たとえば、「1万円以上の買い物は3日考える」「衝動買いは月に1回まで」「外食は週2回まで」といったマイルールを設定すると、無駄な支出を減らしやすくなります。
これは節約のためだけでなく、自分にとって本当に価値のあるものは何かに向き合うことができる効果もあります。
2-3お金の使い方(その3):「モノより経験」にお金を使う
貯蓄上手な人は、単にお金を貯めることが目的ではなく、「お金の使い方」に対する意識が高いことが特徴です。特に、「モノを買うよりも経験に投資する」傾向があります。
例えば、高級ブランドのバッグを買う代わりに、自己成長につながるスキルアップ講座を受講したり、思い出に残る旅行に出かけたりすることで、長期的な満足度が高まると考えています。
また、健康や人間関係など、お金には換算できない価値を重視する傾向もあります。
経験にお金を使うことは、将来的に収入アップにもつながる可能性があるため、「お金の使い方」を見直すことで、貯蓄と自己投資を両立できるようになるでしょう。
3まとめにかえて
いかがでしたでしょうか。
年収の額に関係なく貯蓄がうまくいく人は、日々の生活の中でちょっとした工夫を積み重ねています。
キャッシュレスや後払いなど、簡単に決済を行うことができるようになったことで、意図せず支出が増えてしまうこともあるのではないでしょうか。
これまでの自分のお金の使い方を見直し、無理なく実践できる方法があればまず取り入れることから始めてみてはどうでしょうか。
毎日の生活を少しずつ見直しながら、自分に合った貯蓄スタイルを見つけていきましょう。
4参考資料
 執筆者
執筆者



-1.webp?width=256&s=1.0)